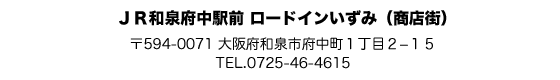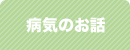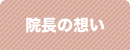次のような症状でお困りの方へ
| 耳が痛い、かゆい、膿や汁が出る、 聞こえにくい、耳鳴りがする、 耳がつまる感じ、めまい など | ➡ | みみの病気 外耳炎、中耳炎、耳あか、 難聴、耳管狭窄症、メニエル病 など | ||||
| 鼻水、鼻がつまる、くしゃみ、鼻血、 鼻のまわりや頭が痛い、 においがわからない、鼻がにおう など | ➡ | はなの病気 アレルギー性鼻炎、花粉症、 かぜ、副鼻腔炎(ちくのう)など | ||||
| のどや舌が痛い、せき、たん、 声が出にくい、のどがつまる、 味がわからない など | ➡ | のどの病気 かぜ、口内炎、扁桃炎、喉頭炎、 声帯ポリープ、喉頭がん、舌がん など | ||||
| その他 いびき(睡眠時無呼吸)、顔面神経まひ、補聴器のことなど何でもご相談ください。 | ||||||
病気のお話 子供がかかりやすい病気
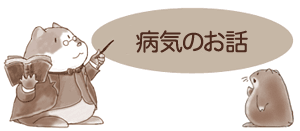
- 急性中耳炎

たいてい風邪をひいた後に、急に耳が痛い、耳から汁が出るといった症状で始まります。鼓膜の奥に膿がたまるので聞こえにくくなります。時に発熱も伴います。
鼻汁に含まれる細菌が原因となりますので、耳の消毒とともに、鼻の症状をしっかり治すことが大切です。痛みがとれても、聞こえにくい症状が治るまで治療しましょう。だいたい2週間ぐらいの通院で治ることが多いですが、鼻の症状がひどい方は耳の症状が落ち着いても鼻の治療を続けます。当院では「鼓膜切開が他の医療機関より圧倒的に少ない」ことが特徴です。 - 滲出性中耳炎

鼓膜の奥に水がたまるため、聞こえにくい、耳がつまる感じがする症状がおこります。痛みはほとんどありません。幼児では自分で症状をうまく表現できないため、テレビの音が大きい、聞き返しや聞き間違いが多い、言葉の発達が遅いといったこと、あるいは検診でたまたま指摘を受けることで見つかります。鼻がつまって耳抜きがうまくできない子によくおこります。
大切なのは鼻づまりを治すこと、通気処置(ガッコとかラッパと言いながら鼻から耳に空気を通す)を繰り返しおこなうこと。急性中耳炎と違って治療に時間がかかりますが、たいてい3カ月近くで改善します。治りにくい例では鼓膜に小さなチューブを挿入する手術をおこないますが、普段の処置をしっかりおこなえば9割以上は手術が必要になることはありません。 - 異物

子供はなぜか手にしたもの、小さなおもちゃなどを鼻や耳に入れて遊びたがります。特に3歳児ぐらいが一番多いです。無理に取らないですぐに来院されることをお勧めします。余計に奥に入って取れにくくなります。
片方だけ青ばなが続くので診察したら、鼻の中に異物が見つかったということもあります。 - 扁桃肥大、アデノイド肥大

いびき、睡眠時無呼吸症候群の原因になります。アデノイド肥大は鼻の一番奥にある扁桃のひとつ(咽頭扁桃)が大きくなることで、いびき以外に鼻づまりの原因となったり、滲出性中耳炎を治りにくくしたりします。
扁桃炎を繰り返す子供に多い傾向がありますが、扁桃炎にほとんどならない子供でも認められます。扁桃肥大やアデノイドは就学時の頃にもっとも大きくなり、それ以降成長とともに小さくなっていきます。そのため、経過観察し、症状がひどい場合は手術で取り除きます。 - アレルギー性鼻炎
 、花粉症
、花粉症
くしゃみが多い、鼻水、鼻がつまる、目のかゆみ、鼻血が多いといった症状がありますが、熱が出たり、鼻水が粘っこくなるのは風邪ひきです。
アトピー性皮膚炎やぜんそくを持っている子供はなりやすいです。幼児期ではハウスダストが原因となっていることが多いです。年齢があがるほど花粉症も多くなります。成人ではスギ・ヒノキ花粉症(2月下旬〜4月)が多いですが、子供ではカモガヤなどのイネ科雑草(4月下旬〜6月)やブタクサなどのキク科雑草(9月〜10月)の花粉症がよくみられます。
 イヌやネコ、ハムスターといった動物アレルギーもみられます。血液検査でアレルギーの原因を調べることが可能ですが、血液検査での抗体検出率は約80〜90%で、血液検査だけで必ずすべてがわかるわけではありません。しかしアレルギー性疾患では予防対策が重要ですので、アレルギーの原因を把握しておくのはよいことです。
イヌやネコ、ハムスターといった動物アレルギーもみられます。血液検査でアレルギーの原因を調べることが可能ですが、血液検査での抗体検出率は約80〜90%で、血液検査だけで必ずすべてがわかるわけではありません。しかしアレルギー性疾患では予防対策が重要ですので、アレルギーの原因を把握しておくのはよいことです。 - 小児副鼻腔炎

いわゆる蓄膿(ちくのう)ですが、大人にくらべると治りやすいです。治療の最大目的は副鼻腔内にたまる鼻汁を排泄させること。そのためには繰り返しの処置が大切です。薬も手術も目的は同じです(小児で手術を行うのは大きな鼻茸がある重症例に限ります)。
3、4カ月の通院で改善することが多いですが、アレルギー性鼻炎を合併していると治りにくくなります。また一時良くなっても風邪をひくと再発を繰り返すので、その都度治療しなければなりません。成人まで持ち越すと治りにくくなるので、それまでに治しておく必要があります。 - 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

ムンプスウイルスに感染して発病します。耳が痛いという場合、最初に中耳炎や外耳炎との鑑別が必要です。熱はないかあっても38℃くらいです。潜伏期間は平均18日(±7日)ですが、約30%は全く無症状の人がいます。耳の下(耳下腺)が腫れますが、片側だけの人もいます。両側が腫れる人はまず片側、数日遅れて反対側も腫れることがよくみられます。だいたい発症後10日ぐらいで回復します。合併症として注意したいのは、1万人に1人ぐらいの割合で一側性の高度難聴をきたすことがあります。
参考までに反復性耳下腺といい、繰り返し耳下腺がはれることがあります。流行性耳下腺炎と違い他人には移りません。細菌感染が原因なので、その都度抗生物質で治します。中学生ぐらいになればたいていかからなくなります - ヘルパンギーナ
 、手足口病
、手足口病
のどが痛くなるので耳鼻科でよく遭遇する疾患です。ほとんどはコクサッキーウイルスによるもので自然治癒しますが、エンテロウイルス71によるものは脳炎や髄膜炎を合併する重症例があり注意が必要です。
毎年6月〜7月に流行します。いきなり39℃ぐらいの高熱で始まり、2、3日で解熱します、そのころから特徴的な口内炎が多発して、ご飯を食べたがらなくなります。だいたい数日で自然に治ります。手足口病は名前のごとく手や足に多数の小水疱を伴います。